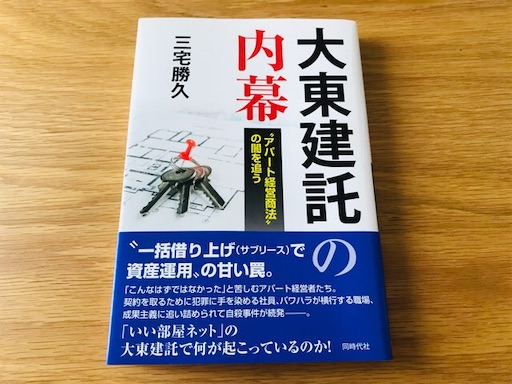
2018年発行のルポルタージュ本「大東建託の内幕」(三宅勝久 著/同時代社)を読みました。
ジャーナリストである著者が、2010年から2017年にかけて大東建託について取材、執筆した記事を一冊にまとめて加筆修正した一冊です。
内容の9割は、大東建託の社内の超絶ブラックっぷりと、物件の家主(オーナー)がどれだけ痛い目を見ているかについて。
あとの1割(0.5割)は大東建託施工の賃貸物件に住んでる住人から寄せられる問い合わせについて。
営業社員の話、管理社員の話、家主(オーナー)の話、立ち退きを要請された人の話など、具体的事例が生々しくつづられています。
二年間契約取れなければクビ、残業100時間はごく普通。過酷なノルマとパワハラ。立地審査の偽造、架空契約、工事費の水増し。などなど。
読んでいるだけで胃が痛くなるような内容ばかりなのですが、セリフや描写が具体的でリアルなので、怖いもの見たさで一気読みしてしまいました。
ぶっ飛んだ内容ではあるものの、過去に2軒、大東建託の賃貸物件に住んだことがある元住人として、納得できる部分が多い一冊です。
印象に残った部分の読書メモと感想をまとめます。
建物の不具合と急増する入居者のクレーム。
茨城県の営業所で大東建託が建てた賃貸アパートの管理業務をしていた山口(仮)さん。
業務内容は家賃回収や入退去の手続き、建物の不具合や騒音などの苦情対応等。明け方まで勤務、土日出勤は当たり前。大半はサービス残業とのこと。
入社後3年ほどは楽な職場だと感じていたが、2000年ごろから状況が一変。(ちょうど大東建託がアパート建設を急増させはじめた時期)
隣がうるさいというのは以前からあったが、雨漏りをはじめとする建物の不具合の苦情が頻発するようになり、入居者のクレームが急に増えたそう。
床下から水が湧いてきたという苦情も経験した。屋根の隙間から漏れた雨水が壁を伝って一階の床下にたまり、床上浸水を引き起こしたのだ。大雨のときだった。
また、水道の漏水や、台所の排水管から汚水が漏れたという苦情がくることもあった。流し台の床板が水に濡れて傷んでいるのを何度も目にしたと山口さんは言う。
もちろん、「水関係」以外の苦情も多々ある。
・玄関の木製ドアが開かなくなる。
・床板が沈む。
・壁がぐらつく。
・基礎コンクリートにひびが入った。
・駐車場のアスファルト舗装がデコボコになった。
そんな不具合にも対応した。苦情が来るのは一定の年数が経って古くなった建物だけではない。新しい物件でも問題が起きた。(44、45ページ)
そして「経年劣化でなく、施工不良、あるいは構造上の問題ではないか」と山口(仮)さんは考え始めます。
じっさい、家主からはよくこう言われたと言う。
「手抜き工事じゃないか。会社負担で修繕工事をすべきだろう」
もっともだと思う例は少なくなかった。床の沈みの原因を調べてみると、束(支柱)の底に基礎石がなかった。ブロック塀のぐらつきは、あるべき鉄筋が入っていないせいだった。天井裏から産業廃棄物が見つかったこともある。(45ページ)
私が住んでいた物件の場合、水回りと建て付けは大丈夫でしたが、2軒とも他の部屋の浴室のにおい(ソープやお風呂用洗剤の香り)が、換気口(もしくは排気口?)を通してこちらの部屋まで入ってきていました。
築浅の綺麗な鉄筋コンクリート造物件で、窓を閉め切り換気扇もつけていない状態でも漂ってきていたので、やはり構造上の不具合だったのでは、と気になるところです。
大東建託側が認めた施工不良の具体例。
以下は、ある民事調停で大東建託側が認めた問題点とのこと。
・雨漏り。屋根立ち上がり部の笠木板金、立ち上がり板金納まり不良
・内部雨漏れでプラスターボードが汚れている
・腰コンクリートブロックのクラック(割れ)
・事務所の巾木が合板になっている(設計と異なる)
・階段レベル納まり悪い
・2階廊下の排水溝の勾配不良
・2階廊下クラック
・水切り下端モルタル仕上げが不良
・鉄骨部及びボルトのタッチアップ(腐食防止の塗装)がされていない
・給水管の吊りバンドがない
・吊戸棚内配線がむき出しになっている
・床レベル不陸(水平になっていない)
・和室襖の取手が傾いて取り付けられている
・屋根材(コロニアル)の数が足りていない。屋根材が割れている
・棟おさえ板金材の浮き
・軒先の歪み
・外壁材のひび割れ
・外部中階段の踊り場に雨漏れあり。鉄骨に錆が発生
・和洋室に換気レジスターがない
・壁巾木の一部に下地がない(壁の裏側に骨材が入っていない)
・駐車場の汚水枡の蓋が、設計では鉄製なのに樹脂性を使用
・台所床にきしみや沈む箇所あり
・壁がはらんでいる(ふくらんでいる)(51、52ページ)
安っぽい建材。
大東建託のアパートオーナーになることにした永峰(仮)さんの話。
やがて工事がはじまった。ここではじめて永峰さんは複雑な気持ちに駆られる。というのは、大東建託が建てているアパートが安っぽかったからだ。柱がなく、壁板を組み合わせただけの「2×4」(ツーバイフォー)と呼ばれる工法である。建材も、樹齢が若い輸入材を薄く剥がして接着剤で貼りあわせた合板だ。(120ページ)
永峰さんはもともと老舗の材木製材業として、伝統的な日本建築を手がけてきた方。これまで、厳選した材木を丁寧に加工し、百年でもゆうにもつ木造建築に使うという、本物の木造を誇りとしてきました。
そんな永峰さんにとって、大東建託の建物は雲泥の違いがあったとのこと。
「せめて材木だけでも自分たちで調達させてもらえないだろうか」と永峰さんは大東建託にかけあった。そのほうが工費が安くなるし、良い材料が使える。
だが相手は即座に拒否した。大東建託が指定する業者の建材を使わなければ一括借り上げはできないし、客付けもしないというのだ。永峰さんは引き下がるしかなかった。(121ページ)
建物に不安を覚えた永峰さんでしたが、すぐに入居者で埋まり、最初の10年は順調だったそう。
そして10年が経ち、契約通り大規模修繕を行いました。が、なぜか空室が増えます。すると、家賃引き下げを求められました。断ると「客付も家賃保証もしない」と言われたとのこと。
問題の元凶は「株価至上主義」。
「役員にとって株価が上がればより多くの報酬がもらえる。株をつり上げることしか頭にない」(古橋執行委員長)
大東建託の問題経営の背景には株価至上主義がある。それこそが不正を多発させている元凶だというのが労組の分析だ。(146ページ)
「手数料や家賃収入で稼ぐのでなく、アパートを建てることで稼いでる」という状況とのこと。
「顧客の利益はそっちのけで、自分の利益だけ追求する」というのはよく聞く話です。
これって、結局はどんどん客が離れていって最後は誰もいなくなるという、自分で自分の首を絞めてる構造な気がするのですが、そういうことは経営陣はあまり考えないのかな、と毎回不思議に感じます。
管理者養成学校という軍隊式の合宿研修。
大東建託では管理者につくと、「管理者養成学校」という約2週間の軍隊式の合宿研修に参加させられるのだそうです。
管理者養成学校の問題については、労組が改善を訴えた結果、合宿の期間が従来の2週間から6日間へと大幅に減らされた。
大声で叫んだり夜間何十キロも歩行させる「訓練」も中止された。労組が勝ち取った大きな功績だ。(148ページ)
何その訓練。何その功績。あまりに謎な内容だったので思わずメモ。
感想。
元住人の視点で読んだので、メモも物件の構造についてのものが主なのですが、本書では社員や家主(オーナー)たちの重い証言が続きます。読んでいて胃が痛くなるエピソードばかりです。
特定のスポンサーを持たないフリーランスのジャーナリストだからこそ切り込めた本なのだと感じます。
実際、出版直前と出版後の2度、大東建託の代理人弁護士から出版社宛に、発行停止と流通した書籍の回収を求める内容証明郵便が届いたのだとか。(結局2020年1月時点で提訴はされていないそう)
私自身は、一人暮らしを始めてから約15年の間に13軒の引っ越しをしており、そのうちの2軒が大東建託でした。(鉄骨造アパート1軒と鉄筋コンクリートマンション1軒)どちらも生活音が漏れすぎる壁の薄さに耐えきれず、それぞれ約半年で退去しています。
もちろん、たまたま運悪くそういった物件に当たってしまっただけかもしれませんが、 二度とここの賃貸物件は借りない、と決意するには十分でした。
ちなみに一人暮らしの最初の1軒目はレオパレスで、そこも隣人の電話の内容がわかるほど生活音が漏れまくり。その約10年後に住んだ大東建託の2物件は、当時のレオパレスを思い出させました。
そんな中、2018年にレオパレスが社会問題になり、じゃあこちらもそのうち社会問題になるのかな、と思っていたところ、書店で本書を見つけた次第です。
こういった住人に優しくない構造の物件が多いのだとしたら、それを建てた会社側や家主側の内情もよほど荒れているのだろうなと思っていたのですが、想像以上でした。
生々しすぎて読んでるうちに胃がむかむかするけれど、どんどんページをめくってしまう。一気読み。あくまでも「アパート経営商法の闇」がメインなので、住人の話は間接的に少ししかなかったのですが、充分でした。
レオパレスの施工不良が社会問題になったのも、やっとここ数年のことなので、不動産業界ってこういうブラックさが本当に隠されていて闇深いよなと感じます。
レオパレス問題も表沙汰になりましたし、本書ラストにあったように、大東建託もそのうち大々的に社会問題化するのかもしれません。
家賃のクレカ決済が可能だったり、入居審査や退去のスムーズさ、部屋の内装や設備のキレイさなど、いい部分もあるので、もったいなさすぎる話です。
健全に建物を建てていれば、入居者も長く住むし、大東建託も稼げるだろうにな、と思っていたのですが、大東建託が家主に保証する家賃保証について知ったら、なるほど、むしろ入居者がすぐ出て行って、空室が増えることで、それを理由に家賃自体を下げさせる→保証する家賃総額を減らすことができるので、ビジネスとしては逆に好都合なのかな、と感じました。
本書を読むだけでも充分驚くのですが、Amazonの本書のページで不動産関係者らしきレビューを読むと、こういった内容は不動産業界あるあるらしく、さらに驚きます。
家主側も住人側も、「上場企業だし、長年生き残ってる会社なんだから、ちゃんとした会社なんだろう」と簡単に信じてしまわず、関わる前には口コミなどを調べるべきだな、と痛感しました。
ちなみに、大東建託の不良建築については、本書の続編「「大東建託」商法の研究」(2020年発行)で語られています。続編も一気読み必至の一冊です。